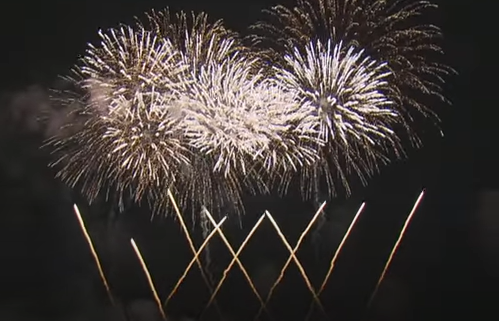-

-
【2025】第366回 筑後川花火大会(福岡県久留米市)
第366回 筑後川花火大会とは 第366回 筑後川花火大会は、1650年の水天宮落成祝賀を始まりとし、360年以上の歴史を持つ久留米市の花火大会。 福岡県を代表する花火大会であり、西日本有数の規模を誇 ...
続きを見る
国内有数の歴史を持つ「筑後川花火大会」の基本情報

福岡県久留米市の夏の夜空を彩る「筑後川花火大会」。
毎年数十万人が訪れるこの花火大会は、その歴史の長さと規模の大きさで西日本を代表する花火イベントとなっています。
この記事では、そんな筑後川花火大会が一体「いつから」始まったのか、その360年以上にもわたる壮大な歴史を紐解いていきます。
西日本最大級!筑後川花火大会の規模と特徴
筑後川花火大会の最大の魅力は、なんといってもその圧倒的なスケールです。
打ち上げ数は約15,000発(※年によって変動あり)と、西日本最大級の規模を誇ります。
さらに大きな特徴として、打ち上げ会場が2つに分かれている点が挙げられます。
- 京町会場
- 篠山会場
この2つの会場から同時に花火が打ち上げられるため、筑後川の広大な水面を舞台に、ワイドで迫力満点の光のショーが繰り広げられます。
特に、川面に映る仕掛け花火「ナイアガラ」は、息をのむほどの美しさです。
2025年の開催情報
筑後川花火大会は、その起源である水天宮の祭礼にちなんで例年8月5日に開催されており、2025年も8月5日に開催されます。
基本情報は以下の通りです。
| 大会名 | 第366回 筑後川花火大会 |
|---|---|
| 開催地 | 福岡県久留米市 |
| 打ち上げ数 | 約15,000発 |
| 開催期間 | 2025年8月5日(火) |
| 開催時間 | 19:40~20:40 |
| 荒天の場合 | 8月7日に延期 |
| 会場 | 久留米市水天宮下河川敷対岸、篠山城跡下河川敷対岸 |
| アクセス | JR久留米駅から徒歩10分 |
| 公式サイト | 第366回 筑後川花火大会 |
筑後川花火大会の起源は江戸時代!いつから始まった?
西日本最大級の規模を誇る筑後川花火大会ですが、その歴史はいつから始まったのでしょうか。
結論から言うと、その起源は370年以上も昔の江戸時代にまで遡ります。
現代のような大規模なイベントではありませんでしたが、今に続く伝統の第一歩が確かにここから始まりました。
始まりは1650年(慶安3年)の「水天宮奉納花火」
筑後川花火大会の直接のルーツは、1650年(慶安3年)に行われた「水天宮(すいてんぐう)」の奉納行事とされています。
この年、全国にある水天宮の総本宮である「久留米水天宮」の社殿が、現在の場所(福岡県久留米市)に完成しました。
その盛大な落成祝いとして、筑後川の河畔で花火を打ち上げたのが、この花火大会の始まりとされています。
当時は「花火大会」というよりも、あくまで神事の一環である「奉納花火」で、水神様への感謝と、人々の安全や豊作を願う意味が込められていたとされています。
発祥のきっかけは久留米藩2代藩主・有馬忠頼公
この歴史的な奉納花火を発案し、実行した人物こそ、当時の久留米藩2代目藩主であった有馬忠頼公です。
有馬家は代々、水天宮を篤く信仰していました。
忠頼公は、無事に社殿が完成したことを祝い、領内の繁栄と災厄消除を祈願するために、この奉納花火を命じたと伝えられています。
一人の藩主の敬虔な祈りが、数百年もの時を経て、今や数十万人が楽しむ一大イベントへと繋がっていると考えると、非常に感慨深いものがありますね。
360年以上にわたる筑後川花火大会のあゆみと歴史
1650年に産声を上げた筑後川花火大会の小さな灯火は、その後どのようにして現代にまで受け継がれてきたのでしょうか。
ここからは、江戸、明治、昭和、そして平成・令和へと続く、壮大な歴史の道のりを時代ごとにご紹介します。
江戸時代:長く続いた奉納花火の伝統
奉納花火が始まった江戸時代。その後も花火は水天宮の祭礼には欠かせない行事として、長く受け継がれていきました。
ただし、当時は現在のような華やかな花火大会というよりは、あくまでも神事の一環でした。
筑後川のほとりで打ち上げられる花火を、人々は水神様への感謝や畏敬の念とともに眺めていたことでしょう。
この時代に築かれた「信仰と結びついた花火」という土台が、この花火大会が3世紀以上にわたって続く礎となったのです。
明治~昭和:戦争による中断と復活
時代が明治、大正、そして昭和へと移り変わる中で、筑後川花火大会は地域に根付いた夏の風物詩として、より多くの人々に親しまれるようになっていきました。
しかし、その長い歴史にも断絶の危機が訪れます。
第二次世界大戦の激化により、花火大会は一時中断を余儀なくされたのです。
しかし、平和を取り戻した戦後、人々の「日常を取り戻したい」という強い願いとともに、花火大会は見事に復活を遂げます。
この戦後の復活は、単なるイベントの再開以上の意味を持ち、復興へ向かう人々の心を明るく照らす希望の光となりました。
平成~令和:2会場同時開催スタイルの確立と現在
平成に入ると、筑後川花火大会は大きな進化を遂げます。
現在では最大の特徴となっている「京町会場」と「篠山会場」の2会場からの同時打ち上げという、豪華なスタイルが確立されたのです。
これにより、打ち上げ数は飛躍的に増加し、筑後川の夜空をワイドに埋め尽くす、エンターテインメント性の高い花火大会へと発展しました。
近年では、新型コロナウイルスの影響で中止や規模を縮小しての開催となった年もありましたが、そうした困難も乗り越え、伝統の灯は守られ続けています。
幾多の時代の変化を超えて輝き続けるその姿は、まさに久留米の誇りと言えるでしょう。
なぜ筑後川花火大会はこれほど長く愛されているのか?
370年以上の長きにわたり、一度も途絶えることなく(戦争による中断を除く)受け継がれてきた筑後川花火大会。
なぜこの大会が、時代を超えてこれほどまでに多くの人々から愛され続けているのでしょうか。
その理由は、単に「歴史が古いから」「規模が大きいから」だけではありません。そこには、3つの大きな理由がありました。
理由1:地域に根差した「水天宮」との深い結びつき
最大の理由は、この花火大会が単なる夏のイベントではなく、水天宮総本宮への「奉納花火」という神聖なルーツを持つ点にあります。
安産・子授けの神様として全国的に知られる水天宮は、地元久留米の人々にとっては生活に深く根差した、心の拠り所です。
そのため、市民にとって筑後川花火大会は、先祖代々受け継がれてきた祈りや感謝の象徴。
夜空に咲く一輪一輪の花火に、ただ美しいだけでなく、特別な想いを重ねて見上げているのです。
この精神的な結びつきこそが、他にない深い愛着を生んでいます。
理由2:筑後川の広大なスケールを活かした迫力ある演出
もちろん、エンターテインメントとしての純粋な魅力も欠かせません。
筑後川花火大会は、筑後川という雄大な自然の舞台を最大限に活かした、圧倒的なスケールが自慢です。
2つの会場から同時に打ち上げられる花火は、視界いっぱいに広がる大パノラマを生み出します。
また、名物の「ナイアガラ」は、川幅の広さがあるからこそ実現できる豪華な仕掛け花火です。
「ここでしか見られない特別な花火体験」が、毎年多くの人々を惹きつけ、感動させています。
理由3:地元の人々の想いと努力
そして何より、この伝統を未来へ繋ごうとする地元の人々の熱い想いと絶え間ない努力があります。
花火大会の企画・運営に奔走する関係者、資金面で支える協賛企業や市民、そして当日会場の安全と美化に努めるボランティアの方々。
こうした多くの人々の「自分たちの街の宝を守りたい」という情熱が、370年以上の歴史を支える原動力となっています。
世代を超えて受け継がれるこの想いこそが、筑後川花火大会がこれからも長く愛され続ける一番の理由なのかもしれません。
筑後川花火大会の歴史に関するQ&A
ここまで筑後川花火大会の長い歴史を紐解いてきましたが、いかがでしたでしょうか。
ここで、筑後川花火大会の歴史にまつわるよくある質問や豆知識をQ&A形式でご紹介します。
Q1. 「筑後川花火大会」という名称はいつから使われている?
A. 戦後、花火大会が神事としての奉納花火から、市民に広く親しまれる夏祭りへと発展していく中で、1965年(昭和40年)から「筑後川花火大会」という名称が使われたと考えられています。
あくまでも、もともとの起源は、前述のとおり「水天宮奉納花火」です。
Q2. これまで中止になったことはある?
A. はい、あります。
最も長く中断したのは、多くの祭りが自粛された第二次世界大戦中です。
近年では、新型コロナウイルスの影響により、2020年と2021年は中止、2022年は規模を縮小しての開催となりました。
また、現在でも台風や集中豪雨などの荒天の際には、観覧者の安全を第一に考え、中止または順延となる場合があります。
Q3. 見どころの「京町会場」と「篠山会場」、どう違うの?
A. 2会場同時開催が大きな魅力ですが、それぞれ特徴が異なります。観覧場所を選ぶ際の参考にしてください。
- 京町会場:仕掛け花火を得意とし、名物の「ナイアガラ」などを間近で楽しめるのが魅力です。緻密で美しい光の演出を堪能したい方におすすめです。
- 篠山会場:迫力満点のスターマイン(速射連発花火)や大玉の打ち上げ花火がメインです。夜空に大きく開く花火の音とスケール感を全身で感じたい方にぴったりです。
どちらの会場も大変な混雑が予想されるため、目的に合わせて早めに計画を立てるのが良いでしょう。
まとめ:筑後川花火大会の歴史を知って2025年の花火をより楽しもう!
今回は、福岡県久留米市が誇る「筑後川花火大会」がいつから始まったのか、その壮大な歴史を深掘りしてきました。
最後に、この記事のポイントを振り返ってみましょう。
- 筑後川花火大会の起源は、1650年(慶安3年)に水天宮へ奉納された花火。
- 戦争による中断を乗り越え、370年以上もの間、伝統が受け継がれている。
- 長く愛される理由は、「信仰」「スケール」「人々の想い」という3つの柱に支えられているから。
こうした歴史的背景を知ることで、2025年の夜空に打ち上げられる一発一発の花火が、また違って見えてくるのではないでしょうか。それは単なる美しい光ではなく、人々の祈り、復興への願い、そして未来へ伝統をつなぐ情熱が込められた、特別な光に見えるはずです。
ぜひ2025年の夏は、歴史とロマンあふれる筑後川のほとりへ足を運んでみてください。3世紀以上にわたる物語が詰まった光の競演を、その目と心で確かめてみてはいかがでしょうか。